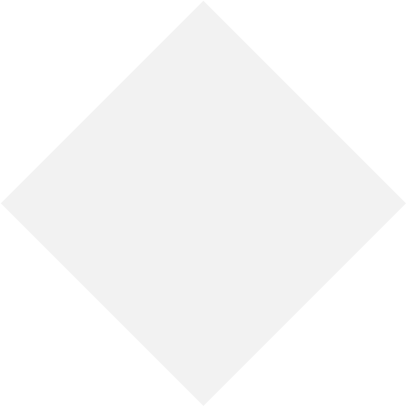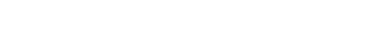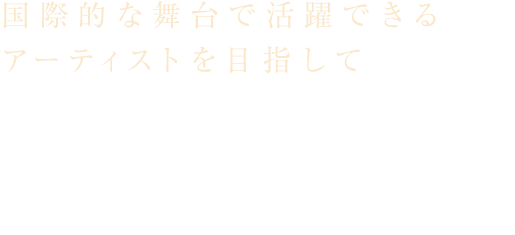


 TOPICS
トピックス
TOPICS
トピックス
-

【イベント情報】尚美ウインドオーケストラ 第48回定期演奏会 [2024.3.4開催]
その他 2023.12.27 掲載
-

【イベント情報】SHOBI WINTER BAND FESTIVAL 2024[2024.1.31開催]
その他 2023.12.27 掲載
-

【イベント情報】SHOBI BAND FESTIVAL 2023[2023.11.8開催]
その他 2023.10.17 掲載
-

【イベント情報】ディプロマ室内楽コンサート[2023.11.11開催]
その他 2023.10.2 掲載
-
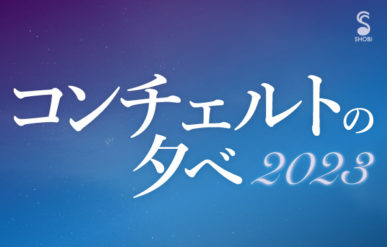
【イベント情報】コンチェルトの夕べ2023[2023.10.21開催]
その他 2023.8.7 掲載
 管弦打楽器学科
管弦打楽器学科
日本を代表する一流の現役プレイヤーたちによる個人レッスンをはじめ、オーケストラ、吹奏楽、マーチングのテクニックを基礎からしっかり指導します。

より広く、深く学びたい